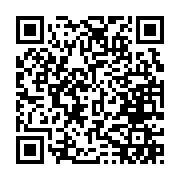玄米菜食(マクロビオティック)とは
穀物や野菜、海藻などを中心とする日本の伝統食を基本とした食事することにより、自然と調和をとりながら健康な暮らしを実現する考え方です。
マクロビオティックは、桜沢如一氏(1893~1966)が、石塚左玄の「食物養生法」の考え方と、東洋思想のベースとなる中国の「易」の陰陽を組み合わせた、「玄米菜食」という自然に則した食事法を提唱したことからはじまります。その後1950年以降、久司道夫氏によってマクロビオティックが体系化され、欧米を中心に広まりました。日本発祥の考え方ですが、初めに広く受け入れられたのは欧米のほうが先。近年、日本でも注目を集めています。
◆マクロビオティックの二大原則
【身土不二】
人間も植物も生まれた環境と一体という意味。例えば、熱帯地域でとれるフルーツには体の熱を下げる働き、寒い地域でとれる野菜には体を温める働きがあり、四季のある日本では季節ごとの旬の食材をとることで体調をととのえることができるという考え方。
【一物全体】
ひとつのものを丸ごと食べる、という意味。食材そのものは丸ごとでバランスがとれており、穀物なら精白していない玄米、野菜なら皮や葉にも栄養があり果実だけでなく全てを摂取することで体に必要なものを得られるという考え方。
◆陰陽バランス
すべてのものに「陰」と「陽」がある、という考え方。
【陰性】遠心力・静かなもの・冷たいもの・水分の多いもの
【陽性】求心力・動きのあるもの・熱いもの・水分の少ないもの
◆食材の陰陽
【陰性の食材】上に向かって育つもの、からだを冷やす作用があるもの
【陽性の食材】地中に向かって育つもの、からだを温める作用があるもの
旬の食材を例にすると、夏のキュウリ(陰性)は、ほてった体から熱をとり、冬のゴボウ(陽性)は、冷えた体を温め、わたしたちのからだのバランスをとる手助けをしていると考えられています。
このような食生活は自然環境との関わりも深く、例えば、地元で採れた野菜はからだに良いだけでなく栄養価も高く、物流に伴うCO2削減にも貢献、いままで捨てていた皮や葉なども食べることでごみの減少にもつながります。
マクロビオティックとは「人も自然の一部であり、自然と調和をとりながら健康な暮らしを実現する」という考え方のこと。特に毎日の食事の重要性を自然との調和を観点に指し示しています。
稲作文化の日本。お米を中心に、しかも精米するまえの玄米を食することは日本人にとって自然なことかもしれません。